生成AIの便益とリスク――政府ガイドラインを起点に中小企業への提言
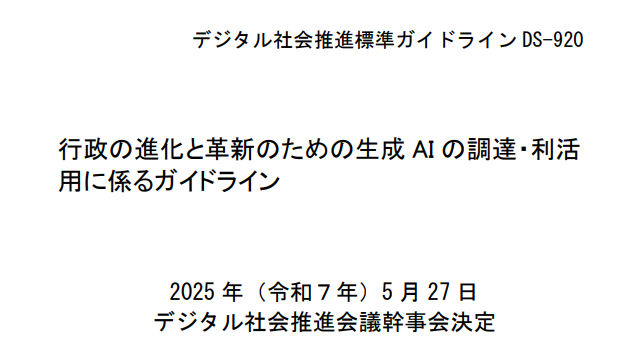
近年、生成AI(Generative AI)は文章・画像・音楽などのコンテンツを自動生成できる技術として急速に広がった。日本政府も行政への応用を模索しており、2025年5月にデジタル庁がまとめた「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」では、生成AIの利点を活かしながらリスクを管理する方針が示された。本記事ではガイドラインに記載された便益とリスクを整理し、これを踏まえて中小企業が生成AIを活用する際のヒントを述べていく。
1. ガイドラインにおける生成AIの便益
生成AIの利点は多岐にわたる。デジタル庁ガイドラインでは、AI事業者ガイドラインを引用しながら、技術の進展に伴って企業や組織が創造的な価値を生み出せることを強調している。具体的には以下の点が挙げられる。
- 運営コストの削減と業務効率化:生成AIを活用すると事務作業の自動化が進み、人手と時間の削減につながる。行政文書のドラフトやメール文案をAIが作成すれば担当者は微調整だけで済み、挨拶文や要点整理が短時間で可能になる。
- 新製品・サービスの創出:既存事業のイノベーションを加速させる新製品・サービスを生み出せる。生成AIは企画立案の支援にも有効で、AIが提示した企画案を基に内容を深掘りすることで効率的に企画書を作成したり、指定テーマに関する新たな気付きを得たりできる。
- 組織変革と情報分析能力の向上:多様な分野や展開モデルに応用でき、組織の変革や人材の能力向上を促す。例えば過去の文書調査や情報収集をAIに任せれば、作業時間を大幅に短縮し期限超過のリスクも軽減できる。
- 政策や文書の質の向上:イベント情報をSNS記事にする場合、複数の案をAIが提案し、それぞれの長所を取り入れることでより洗練された記事が作成できる。また報告書の評価や対策案の検討をAIに支援させれば、具体的で多角的なフィードバックが得られ政策文書の質を高められる。
- 既存システムの利便性向上:問い合わせ分類や検索業務に生成AIを活用すると、既存システムの分類・検索精度が向上する。これにより窓口業務の負担を軽減し、住民や利用者へのサービス品質が向上する。
ガイドラインはこうした便益を踏まえて各府省庁に積極的な利活用を呼びかけ、デジタル庁がユースケースを想定した技術検証やアイデアソンを進めるとしている。行政分野での利活用事例は中小企業にも適用できる点が多く、後述するヒントの基盤となる。
2. ガイドラインにおける生成AIのリスク
生成AIの導入は大きな利点をもたらす一方で、技術面・社会面・経済面など様々なリスクが存在する。ガイドラインではAI事業者ガイドラインを基に分類されたリスク例を提示している。主な内容を整理すると次の通りである。
2.1 技術的リスク
- 学習・入力段階のリスク:不正データの混入やプロンプトを通じた攻撃によりAIの出力が意図的に操作されるリスクがある。学習データの偏りによってAIが差別的な出力を生成することも問題であり、適切なデータ管理とガバナンスが不可欠である。
- 出力段階のリスク:偏った出力や差別的な出力、事実と異なる「ハルシネーション」などが生じ、利用者を誤導する。ブラックボックス化によって判断過程が説明できず、有事の際に説明責任を果たせない恐れもある。
- セキュリティ上のリスク:AIシステムへのサイバー攻撃、プログラム生成で誤ったコードが生成されることによる事故リスクなども含まれる。さらに生成AIに入力した情報がモデルに残る場合、機密情報が外部サービス経由で漏えいする可能性がある。
2.2 社会的リスク
- 倫理・法のリスク:個人情報を適切な同意なしに利用するとプライバシー侵害となり、生命や健康に関わる分野では誤動作による事故が発生する懸念がある。採用活動等でAIに過度に依存すると差別や説明責任の欠如が問題となる。
- 悪用や過度な依存:詐欺目的でAIが悪用される可能性や、AIと会話する利用者が精神的に依存状態になる事例が報告されている。企業が重要な意思決定をAIに任せきりにすれば、批判や法的責任を問われかねない。
2.3 経済的リスク
- 知的財産権侵害:生成物が他者の著作物と同一・類似している場合、著作権や商標権の侵害にあたる恐れがある。権利者からの訴訟リスクも現実的で、AI利用企業は生成物の権利関係を事前に調査する必要がある。
- 金銭的損失・機密情報の流出:AIの出力が他者の権利を侵害すると損害賠償を負うリスクがある。入力した機密情報がモデルから漏えいする懸念もあり、韓国企業ではChatGPTに機密情報が流出した事案が発生した。
- 労働市場への影響:AIの導入により失業リスクや格差の拡大が懸念される。一部のAI開発者にデータや利益が集中することで、公平な競争が損なわれる可能性もある。
2.4 情報空間と環境へのリスク
- 偽情報や世論操作:生成AIによる偽情報やディープフェイクが拡散され、選挙や世論に影響を与える懸念がある。レコメンド機能で似た意見ばかりが表示される「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」によって極端な考えに偏るリスクも指摘されている。
- 多様性の喪失:同じAIモデルを多くの人が同じ使い方で利用すると、意見や回答が画一化し、社会全体の多様性が失われる懸念がある。共通アルゴリズムが金融市場で使われると不安定性が増す可能性も指摘されている。
- 環境負荷:AI開発や利用には大量の電力が必要で、エネルギー消費と環境への負荷が増大する。サステナビリティの視点で省エネ技術の導入や利用量の抑制が求められる。
2.5 政府固有のリスク
ガイドラインは行政利用に特有のリスクも挙げる。政策に関わる業務において政治的中立性を逸脱する表現を生成する危険や、特定のモデルに依存することによるコスト増・バイアスの固定化、文化・歴史的背景を無視した出力による誤発信などがある。また業務判断の根拠が不明瞭になり説明責任を果たせない、ベンダーロックインによってコストが増加する、翻訳サービスに生成AIを使うことで誤訳が法的問題を引き起こす、といったリスクも指摘されている。こうしたリスクは行政に限らず企業にも該当するため、利用の際には慎重な検討とガバナンスが必要だ。
3. 中小企業が生成AIを活用するためのヒント
東京商工会議所が2024年に作成した「中小企業のための生成AI活用入門ガイド」では、ChatGPTをはじめとする生成AIの基本概念、活用事例、注意点がまとめられている。
3.1 利用目的を明確にし、身近な業務から導入する
東京商工会議所の調査によれば、2023年時点でChatGPTを含む生成AIを「活用している」と回答した中小企業は5.7%、「現在活用していないが今後活用を検討している」が29.6%であった。活用企業の多くはコンテンツ作成・校正や情報収集、アイデア出し、言語翻訳に利用している。まずは会議録や議事録の要約、メール文案の作成、企画書の骨子づくりなど身近な業務からAIを試し、メリットと課題を把握すると良い。生成AIは長文の要約や翻訳、アイデアのブレーンストーミングに優れており、少人数の企業でも業務効率化や人手不足の補完に活用できる。
3.2 出力の正確性を必ず確認する
ガイドでは、生成AIがインターネット等の大量データから潜在パターンを学習して最も「確からしい」コンテンツを生成するため、必ずしも正確な情報とは限らないことが強調されている。生成AIの回答は自信ありげでも誤情報や古い情報を含むことがあり、ファクトチェックが不可欠だ。中小企業ではAIが生成した文章や分析結果をそのまま採用せず、複数の信頼できる情報源と照合する体制を整える必要がある。
3.3 個人情報・機密情報を入力しない
ChatGPTなどの生成AIサービスでは、入力された情報がモデルの学習に利用される可能性があるとされ、秘匿性の高いデータを入力すると第三者に流出する危険がある。個人情報保護法は、民間事業者に対し個人情報の取得・利用・保管・第三者提供の各段階で適切な取扱いを義務付けており、違反すると行政処分や刑事罰、損害賠償等のリスクを負う。氏名や連絡先、パスワード、顧客情報、財務データなど機密情報はAIサービスに入力せず、機密を扱う場合はオンプレミスや閉域ネットワークを使ったAIモデルの導入を検討する。AIのデータ保持設定をオフにできる機能もあるが、完全な削除が保証されていない点に注意する。
3.4 利用規約と著作権に留意する
生成AIサービスの利用規約を遵守し、特に商用利用や著作権に関する条件を確認する。ChatGPTの利用規約では、金融・医療・法律分野のコンテンツやニュース生成など消費者向けコンテンツを提供する場合、AIが生成したことや潜在的な限界を明示する免責事項の提示を求めている。生成物が既存の著作物に類似している場合は権利侵害となる恐れがあり、既存の著作物名や作者名をプロンプトに入力しない、特定の作者の作品のみを学習させたモデルを利用しない、生成物を利用する際は類似性を調査する、といった対策が推奨されている。商標や意匠登録の確認も欠かせない。
3.5 社内のAIリテラシー向上とガイドライン策定
AIを全社的に活用するには、経営者と従業員全員がリスクと限界を理解し、組織としての方針を共有することが重要である。東京商工会議所のガイドでは、社内利用ガイドラインの策定を推奨しており、日本ディープラーニング協会がひな形を公開している。中小企業でも、生成AIの利用範囲や禁止事項、データ管理方針、著作権や個人情報保護への対応などをまとめたガイドラインを整備し、定期的に研修を行うことでAIリテラシーを高める。また、AIに依存しすぎず、人間による確認や判断を残すことで、社会的責任や説明責任を果たす体制を作る。
3.6 段階的に高度な活用へ進む
初期段階では既存の生成AIサービスを活用して業務効率化を図り、一定の効果が確認できたら自社データと連携したカスタマイズAIや自社向けのプロンプトエンジニアリングに進むのが良い。生成AIはマーケティング・顧客対応・商品デザインなど多くの分野に応用できるが、技術的リスクや社会的影響も大きいため、効果検証とリスク評価を繰り返すことが求められる。クラウドサービス利用時にはベンダーロックインを回避するため、複数サービスを比較し、将来的に乗り換えやすい構成を検討する。また、環境負荷を考慮し、必要な計算資源の適正利用や省エネの取り組みを行う。
4. おわりに
生成AIはコスト削減やイノベーションの加速、業務効率化に大きな可能性をもたらす一方、技術的・倫理的・経済的・社会的リスクが存在する。デジタル庁のガイドラインは政府の調達・利活用における便益とリスクを整理し、AIガバナンス体制の構築とリスク管理を表裏一体で進める必要性を示している。中小企業が生成AIを活用する際も、利用目的を明確にし、出力の正確性を確認し、個人情報や機密情報を入力しないこと、著作権や利用規約を遵守すること、社内ガイドラインを策定してリテラシーを高めることが鍵となる。さらに、個人情報保護法など現行の法令を正しく理解し、適切な管理体制を整えることで、AIの利点を享受しながらリスクを低減できる。生成AIを「魔法の杖」と捉えるのではなく、あくまで補助的なツールとして位置付け、人間の判断を中心に据えた活用を心掛けることが、これからの企業の競争力向上と持続的な成長につながる。
出典
行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(デジタル庁、2025年5月27日)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/80419aea/20250527_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf
中小企業のための「生成AI」活用入門ガイド(東京商工会議所、第3版 2024年6月3日)
https://www.tokyo-cci.or.jp/chusho/tcci_generativeai_guide_for_smes_ver03.pdf
個人情報保護法とは?企業の義務・対策をわかりやすく解説(BUSINESS LAWYERS、2025年8月19日)
https://www.businesslawyers.jp/articles/1485


